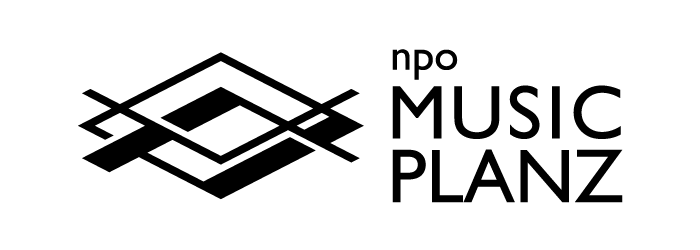コードを理解するための第一歩【理事長コラム】
Contents
音楽理論の核心はインターバル(音程)にあり
音楽理論を詳しく知れば、コード一つから様々な情報が引き出せる。
例えば「A♭△7(エーフラット・メジャーセブンス)」というコードがあるとする。
これは次の4つの音からできている:
- A♭=Root音(ベースの音)
- M3使用=C(M3利用時はコード情報を書き込まない)
- P5使用=E♭(P5利用時はコード情報を書き込まない)
- M7使用=G(コードシンボル△7=M7)
よって
A♭△7=A♭ C E♭ G
という構成音になる。
コードの前提理論
上記のコード構成は前提理論の理解が必要だ
コードとは3度ずつ積み重ねられた(3度堆積)音の集合体である。
3度とは音名が「3」の距離を表す。(これを度数という)
始まりの音A♭の音名は「A」
よって「A」から3度ずつの音「C」「E」「G」が必ず使われる。
そして上記のようにコードネームに記されているコードシンボルから各構成音インターバル(音程)がわかり、
変化記号の有無など正確な音名が確定する。
すなわち、ポピュラー音楽理論の基礎部分であるインターバル(音程)が理解できないと、コードそのものが理解できない。
このインターバルこそが、音楽理論を難しくさせている根幹要素になっている。
世の中で音楽理論が疎ましく思われているのも、インターバルの正しい理解が浸透していないからだ。
「A♭△7」から分かるスケールとの関係
A♭△7コードは、メジャースケールにおけるダイアトニックセブンスコード(Diatonic 7th Chord)の中で、以下の位置に現れる:
- Key of A♭のⅠ(Ionian)
- Key of E♭のⅣ(Lydian)
それぞれのコードに対するスケールとテンション:
Ionian(アイオニアン)
- 構成音:R 9 M3 11 P5 13 M7
- テンション:9=B♭、13=F
- アボイドノート:11=D♭
Lydian(リディアン)
- 構成音:R 9 M3 #11 P5 13 M7
- テンション:9=B♭、#11=D、13=F
- アボイドノート:なし
このように、スケールに含まれるテンションやアボイドノートの違いは、アレンジやアドリブの大きな指針となる。
コードをただ鳴らすだけでなく、その存在位置や使い方までを理解することが、ポピュラー音楽理論の本質的な活用につながっていく。
そして、その根幹要素が間違いなくインターバル(音程)なのだ。
音楽理論の基礎は「インターバル(音程)」
スケールでもコードでもない。
音楽理論において、最初に覚えるべきものはインターバル(Interval)=音の距離と関係性。
インターバルが分からなければ、音楽理論は一生わからない。
裏を返せば、ここを理解することが、すべてのスタート地点になる。
インターバルとは?
2つの音の距離を示す単位。
度数(例:3度)+音程の性質(例:M=長、m=短、P=完全など)で表される。
- F→Aは「M3(長3度)」=半音で4つ分
- F→A♭は「m3(短3度)」=半音で3つ分
- F→A♯は「+3(増3度)」=半音で5つ分
どれも「F→A」ではあるが、シャープやフラットがつくと半音数が変わる。
つまり、度数は3度で同じでも、インターバルはまったくの別物になる。
音楽理論を支える2つのモノサシ
音楽理論は複雑に見えて、実はたった2つの要素で構成されている。
- 半音/全音(鍵盤上の物理的な距離)
- インターバル(度数+音程の性質)
この2つをしっかり押さえれば、コード、スケール、ボイシング、作曲、アドリブ、すべてに応用できる。
通常と異常インターバルの違い
インターバルにはスケール上で自然に成立する「通常状態(normal)」と、意図的に外れる「異常状態(abnormal)」がある。
- 通常インターバル:M(長)、m(短)、P(完全)
- 異常インターバル:+(増)、o(減)
異常インターバルが登場すると、音楽に緊張感や動きが生まれる。
つまり、インターバルを制する者が感情を操る音楽表現を可能にする。
実践で活きるインターバルの使い方|循環コード編
例:C△7 → Am7 → F△7 → G7
[I-VI-IV-V]
例えば「D」音がメロディでずっと鳴っているとする。
各コードに対して
D:C△7←9th[M2]=テンション音
Am7←11th[P4]=テンション音
F△7←13th[M6]=テンション音
G7←P5=コードトーン
という位置付けの音になり「D」というメロディ音の立ち位置が明確になる。
これが「E」になると
各コードに対して
E:C△7←M3=コードトーン
Am7←P5=コードトーン
F△7←M7=コードトーン
G7←13th[M6]=テンション音
となり、先ほどの「D」音とはキャラがまるで異なるトーンとなることがわかる。
これらはメロディ構築の理解の基礎にもなる。
インターバルは“全ての入口”
作曲、分析、演奏、耳コピ。
音楽を深く理解しようとするすべての場面で、インターバルは登場する。
だからこそ、ここを避けて通ることはできない。
むしろ、ここさえ分かれば、他のエリアの学習はさらに楽しくなる。
▼詳しくはこちら
音楽は、何歳からでも学べる
ただし、それは“学校で習う音楽”とはまったく違うアプローチです。
MUSIC PLANZでは、音感やセンスよりも「学び方の構造」を重視しています。
実際に実績が出ているこの学び方は、何より「音楽を続けたい」人に必要な基礎です。
正しく「構造を知る」ことで、誰でも音楽を深く楽しめるようになる。
本気で音楽に向き合いたい方へ
DTMや作曲の基礎はひと通りやった。けれど、どこかで“壁”を感じている。
そんな方にこそ届いてほしい内容です。
小手先ではない、音楽の本質を知りたい方は、ぜひご覧ください。
音楽理論 インターバル 音程の種類 コード構成 音程関係 作曲 音程 理解 循環コード ボイシング メジャーコードとマイナーコードの違い 音楽理論 覚え方