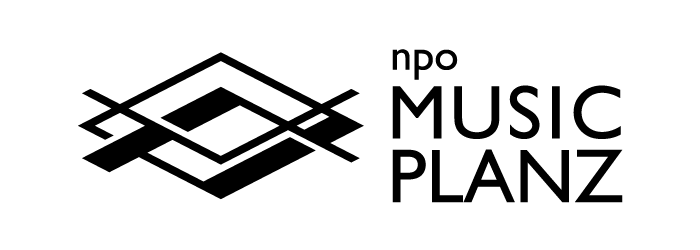「自分の曲のジャンルが分からない」と思ったときに
DTM/音楽制作にて「この曲のジャンルは何?」と疑問に思ったことはないだろうか?
経験上一度はぶつかる問いだと思う。
日本では、ジャンルの意識がさほど細かくない。
リスナーも「K-POP風」「バンドサウンドっぽい」くらいの印象で聴いて十分楽しめてしまう。
Contents
実際のチャート傾向と、ジャンルの幅
いまのJ-POPチャートではフォークロック系が多い。そこにK-POPや、ボカロ系エレクトロニック系が時々混じってくるくらいだ。
実際のジャンルは非常に細かく分かれている。
ジャンルは言うならばリスナーにとっての羅針盤だ。
大昔は
- ロック
- ポップス
- ブルース
- ジャズ
- クラッシック
- カントリー
と、ジャンル分けはとても大まかだった。
しかし、音楽と嗜好の多様化にて、ジャンルの細分化が促進された。
リスナーも既定ジャンルをあらかじめ知っておくことで、膨大なカタログから迷い少なく目的の音源にたどり着くことが容易になったのだ。
たとえば「ロック」も以下のように細分化される(一部抜粋)
- オルタナティブ・ロック
- インディー・ロック
- ポスト・ロック
- プログレッシブ・ロック
- HR/HM
- シューゲイザー
- etc…
このように分類を深めていくことで、自分の音楽も相対化され、座標が明確になる。
ジャンル判別のヒント:歪みとリズム、コードの重なり
ジャンルを見極めるヒントはバンドアンサンブル系ならばギターサウンドにある
- 歪みなし クリーン→ フォーク
- クリーンから程よい歪み(クランチ)でまとまり重視 → ポップス
- 強めのディストーション、圧のあるドラム、寡黙だが存在感あるベース → ロック
コード使い、アンサンブル、リズム隊の音作りも大きな手がかりになる。
あくまで目安だが、こういった「音の質感」はジャンルを考えるうえで重要な材料になる。
ジャンル細分化の極み:Beatportで探るクラブミュージックの世界
ジャンルの細分化が際立つのがクラブミュージック/エレクトロニック系だ。
その世界を垣間見るのにおすすめなのが、Beatport。
世界中のDJたちが、このサイトで音を探している。
ジャンル要素は以下の項目がメイン:
- リズム(ビートパターン、ベースグルーヴ)とサウンド
- BPM(テンポ)
- アイコニックサウンド
「このジャンル名は?」と思ったらまずはザッピングでもいいので聞き込むこと。
ジャンル感覚は、本を読むより「音を浴びる」ことで育っていく。
ジャンルは音楽構造の理解そのもの
今、自分の音楽がどのジャンルに近いかが分かると、何を引くか足すか、出し入れをどう組み立てるかも自然に見えてくる。
ジャンルは、大枠の既定がある中での羅針盤になる。
音楽は、何歳からでも学べる
“学校で習う音楽”とはまったく違うアプローチでのことです。
MUSIC PLANZでは、音感やセンスよりも「学びの構造」を重視します。これは「音楽を続けたい」すべての人に共通な基礎事項です。
この基礎事項を押さえ必要なカリキュラムを習得することで
誰でも音楽を深く楽しめる
ようになります。
このメソッドにて積み上がった実績が全てを証明しています。
▶︎ 実績はこちら
本気で音楽に向き合いたい方へ
DTMや作曲の基礎はひと通りやった。けれど、どこかで“壁”を感じている。そんな方にこそ届いてほしい内容です。
小手先ではない、音楽の本質を知りたい方は、ぜひご覧ください。