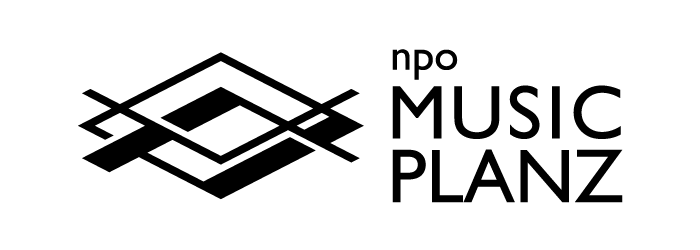失われた“本物の耳”を取り戻す方法【理事長コラム】
Contents
世代間で広がる“耳の性能”のギャップ
音楽を教えていると、世代間にて耳の性能に差があることがわかった。あくまでも平均だが、バブル世代をラストに、それよりも上の年代は耳の性能が良い。そして若くなるとどんどん性能が劣化する。
分岐点:音楽のポータブル化がもたらした変化
このバブル世代に何があったかというと音楽のポータブル化だ。私がまさしくバブル世代だが、この実現については鮮明に覚えている。
音楽を聴き始めた幼少期(1970年代初頭)は、好きな曲を、いつでも聴けるわけじゃなかった。ステレオ機器はまだまだ高く、レコード自体も庶民には高価な代物だった。つまり、音楽そのものが贅沢だったのだ。
テレビやラジオでたまたま流れた音楽に、耳をそば立てる。一度きりかもしれないその瞬間に、全力で聴き取ろうとする。
耳コピという鍛錬が当たり前だった時代
耳コピも簡単なことではなかった。ループもできないレコードや、巻き戻し自体面倒くさいカセットに、何度も耳を凝らして、ほんの一小節を覚えるのに何十分もかけることもあった。
そんな風に、楽譜を使わずに音楽を聴き取る行為(耳コピ)は尋常ではない難易度があった。でも、それが当たり前だったし、その“当たり前”の中で耳を育ててきた。
ウォークマン以後に失われた真剣さ
それが、ウォークマンの登場で状況が一変した。音楽の携帯化はいつでもどこでも楽しめる利便性をもたらした。
だが、そのせいで「いつこの曲が再び聴けるか保証されない」危機感がなくなり、「音を最大限聞き漏らさずに聴く」真剣さが失われていったのだ。
耳性能低下の具体的な症状
- リズムに対するGrid/Resolutionが粗い
- 基本的メジャースケール感覚が薄い
- アボイドへの反応が鈍い
- クラッシュにも無感覚
これは、一般人だけでなく、音楽を志す人にも共通している。
DTM時代の落とし穴:サウンド偏重と“音符エリア”の欠落
今の時代、DAW/DTMにて、ツールを一通り揃えて基礎的How toを学べば、音楽教育を受けなくてもなんとなく楽曲が制作できてしまう。
これはサウンド(音色)偏重が顕著になっていることも加わっているが、音符エリアに精通しているクリエーターは本当に少ない。
音楽の三要素:リズム/音符/サウンド
- リズム:音楽の前提となる基盤
- 音符エリアのシステム
- サウンドエリア
利便性の発展で3.サウンドエリアへの感度は上がった。しかし、その代償として1.リズム、2.音符エリアの感度は削がれてしまった。
取り戻す唯一の方法:真剣に聴くことを繰り返す
- ながら聴きをやめ、聴く時間を区切る
- 一曲を繰り返し、リズム/メロディ/コードを個別に意識して聴く
- 頭の中で再生する(口ずさむ・リズムを刻む)
学び方の構造で耳は変わる:MUSIC PLANZの提案
音楽は、何歳からでも学べる。ただし、それは“学校で習う音楽”とはまったく違うアプローチです。
MUSIC PLANZでは、音感やセンスよりも「学び方の構造」を重視しています。実績が出ているこの学び方は、何より「音楽を続けたい」人に必要な基礎です。
本気で音楽に向き合いたい方へ。
DTMや作曲の基礎は一通りやった。けれど、どこかで“壁”を感じている。そんな方にこそ届いてほしい内容です。